
グラデュウス・マルチリンガルサービス
翻訳サービス
通訳サービス
イベント運営
外国語ナレーション
テープおこし
各種講座
翻訳/通訳セミナー
調査・研究論文
世界最長の道路トンネル「ラーダトンネル」を走るオスロ‐ベルゲンの旅
グラデュウス・マルチリンガルサービス株式会社 山本千雅子
1.はじめに
2003年の9月後半に欧州数カ国の道路関係の研究所等を訪問し、レンタカーで移動しました。その旅の最後にノルウェーの首都オスロから第2の都市ベルゲンまでの約580kmで通った世界最長のラーダトンネル(Laerdal Tunnel)についてご紹介します。
2.オスロ-ベルゲンのルート
ノルウェー国家道路庁を訪問した際にラーダトンネルの資料を貰いました。オスロ-ベルゲン間には2ルートあり、通常、E16を通ります。もうひとつはE6を北上し、オタ(Otta)からA15に、そしてロム(Lom)からA55、ソグダール(Sogndal)からA5でラーダトンネル坑口でE16に合流するルートです。どちらもシーニック(景色がよい)でノルウェーのドル箱観光ルートです。

図1.ラーダトンネルの位置
3.道路構造と運転
同じ距離でも道路構造によって所要時間はまったく異なります。ドイツのアウトバーンではケルン-ハンブルグの420kmは休憩を入れても4時間程度です。ノルウェーの欧州幹線道路E16にアウトバーンのような高速道路を期待していたのですが、残念ながらほんの一部だけでした。
路線名A5のAとは幹線(Arterial)、いわば国道です。道路構造は様々で、アクセスコントロール区間や3車線道路もあれば、2車線分の幅員がとれない郊外部では幹線といえどもセンターラインがありません。
今回の旅のパートナーはコンサルタントのN氏です。平均140〜160 km/hで走行するアウトバーンの運転は私には最高に楽しかったのですが、車両右側がときには車線ぎりぎりだったり(でもそれはN氏も同じ)彼より少々狭い車間距離が原因で「寿命が縮んだ」そうです。N氏の右足は時々ブレーキを求めてばたばたしていました。
4.オスロからラーダトンネルへ
9月27日土曜日。朝、8時30分に出発。まず、オスロからE6で空港方面に向かい、ミョサ(Mjosa)湖の西岸を北上するA33に入りました。このあたりまでE6はアクセスコントロールされた高速道路です。ノルウェーの高速道の制限速度は100km/hです。
オィェヴィク(Ojevik)から峠越えのA28は急峻なノルウェーの地形を縫って走ります。湖と森とフィヨルドのU字谷が美しい景観ですが、勾配・カーブともにきつく制限速度は50〜80 km/hです。アウダール(Aurdal)の手前でE16に入りました。少しは道路構造がよいかも、という淡い期待は裏切られセンターラインのない道が続きます。対向車はスピードも落とさずに狭い道路ですれ違っていきます。
イヴィヒ(Ivih)から景色のよい旧道A53に。標高が上がると植生はハイマツから高層湿原となり、限りなく透明な湖の周囲に避暑用の別荘が並ぶあたりからは、青い空を背景にすでに白い雪に覆われた山々が望めます。絵のような景色、とはこのことでしょうか。湖を源とする流れに沿ってこの高原を下るころにはすっかり景色に魅せられて夢見心地でした。
氷河地形は、山地を源とする流れがV字谷を形成する日本の地形とは違い、いわゆる谷のどんづまりが丘や断崖絶壁で、しかも湖の下流部分にもあります。そしてその丘や山の向こう側はまた別のU字谷です。フィヨルドは内陸深くに伸びているのでときには谷奥が分水嶺となります。河川や湖の下流に向かって走行しているつもりが、流れの方向が変わることもあります。
5.ラーダトンネル
A5を経てラーダトンネル坑口で再度、E16に合流。ラーダ(Laerdal)とアウランド(Aurland)を結ぶ所要時間約20分の世界最長道路トンネルは、以外にあっさりしたものでした。強いインパクトを与えないトンネルであることが、非常に印象的でした。
一番の特徴は、延長24.5kmの1本のトンネルとしてではなく、延長6kmのトンネル4本とドライバーが感じるように設けた3箇所の広い空間です。設計段階で様々な検討が行なわれ、ライトで壁面を演出することとなりました。コンセプトは「日の出」で、ブルーは外から太陽光が射しているイメージ、黄色は暁の輝きです。
この「日の出」の空間で写真を写し、センターのランブルストリップ上も走行してみました。路側は他のトンネルよりはるかに広く、圧迫感がありません。E16には他にも延長16km等、10km超のトンネルがあり、それらの方が閉塞感がありました。
直線で暗いトンネルが10kmも続くと、早く出たいという気持ちから運転速度が上がったり、単調さから居眠しそうになります。これらへの対策がラーダトンネル設計の重要課題で「あっさり」は設計意図の成功に他ならぬわけです。

図2.トンネル内部の広い空間
6.ラーダトンネルからベルゲンへ
フラン(Flan)からフォス(Voss)にかけては、深い氷河湖や針葉樹、急峻な断崖の数々の滝、鏡のような湖等フィヨルド観光の中心です。ダール(Dale)あたりから、2車線道路が続きベルゲン都市圏に入ります。ベルゲンは入江に発展した古い都市で、周囲の数多くの島々と橋梁や海底トンネルで結ばれています。
7.おわりに
ノルウェー国家道路庁によるとオスロ-ベルゲンは、最短経路を休まずに走行して7〜8時間で、休憩や景色を見るために駐停車する回数と時間によって所要時間は変わるとのことでした。この駐停車が曲者、思わず車を止めてしまう景色があまりにも多すぎるのです。途中、道に迷ったり、シーニックバイウェイに迂回したり、最後には予約したホテルを見つけるのに手間取ったりで結局、12時間の旅となりました。
ロードマップと格闘しながらも欧州で最も美しい自然景観とノルウェーの技術を垣間見ました。また、地質や地形条件が違えば使われる技術も異なることを見聞し、「脱常識」の大切さも感じた旅でした。この経験を今後に活かしていきたいと思います。
資料編 ラーダトンネル技術データ
1)経緯
1975年ノルウェー国会は、ラーダとアウランド間の道路を山岳ルートに決定。1980年代に延長20km超のトンネル内の換気を可能にする技術が進展したことから、1992年国会はラーダトンネル掘削を決議。1995年3月15日起工。1999年9月3日トンネル貫通。2000年11月27日竣工。
2)プロジェクト概要
○総建設費: 10.82億ノルウェークローネ
○建設期間: 1995年〜2000年
○トンネル延長: 24.51km
○アクセス兼排気トンネル延長: 2,100m
○トンネル内の広い空間:3箇所(6km間隔)
○年平均日交通量: 1,000台
3)建設工事:ノルウェー国家道路庁:坑口からアウランド側11km、ラーダ側0.8 km。NCC Amlegg 株式会社:アクセストンネル2km。アクセストンネルと本坑との合流点からアウランド側7km、ラーダ側5.7km
地質コンサルタント: NGI北欧地質研究所
4)地質
○ほぼ全体が堅固で乾いた先カンブリア代の片麻岩。破砕帯6箇所。断層1箇所。
○工事中にアウランド側坑口から10kmの破砕帯で岩盤崩落。1000 m3の岩石がトンネルを埋めた。注入コンクリートで岩石を固めた後、岩石とコンクリートの中を新たに掘削。
5)工法
最深部1400mで、ほぼ全体で岩はねが問題。発破後、洗浄・目視点検し、ロックボルト(長さ2.5〜5メートル。亜鉛めっき鋼)、ファイバー補強ショットクリートで一体化。全体でロックボルト20万本、ファイバー補強ショットクリート45,000m3を使用。(ショットクリートだけなので、素掘りのように見える。)
6)空気質の管理
○ラーダトンネルの交通容量は400台/時。
○道路トンネル内空気質には厳しい規制。400台通過までに空気全部を入れ替え。アウランド坑口とテョンダーレン換気兼アクセストンネルの間18kmは1時間で入替。
○トンネル内数カ所で空気質をモニター。汚染濃度に応じて数多くのファンと処理プラントをコンピュータ制御で効率的に運転。
○両端坑口から空気取り入れ。テョンダーレン換気兼アクセストンネルと本坑の合流点のファン2台で汚染された空気を本坑から、粉塵・二酸化窒素除去プラントに送る。トンネル内の粉塵と二酸化窒素の濃度に応じてファンの回転を自動制御。(最大風速5m/s)。
7)粉塵・二酸化窒素除去プラント
○世界初の粉塵・二酸化窒素除去プラント設置トンネル。
○アウランドから9.5kmの延長100mのトンネル内の電気式フィルタで粉塵、特別に開発された大型カーボンフィルタで二酸化窒素を除去。
○80〜90%の粉塵と二酸化窒素を除去。浄化した空気をトンネル内に戻す。
8)保安設備
消火器作動でトンネル両端の交通流入を自動的に遮断し、トンネル内車両には方向転換を指示。また、自動的に非常サービスセンターへ連絡。同時に警察・消防・病院に別チャンネルで通報。
○非常電話(250m間隔)と消火器(125m間隔)は通常よりも短い間隔で設置
○火災等非常時に方向転換や待避場所の確保。3箇所の広い空間(6km間隔)、15箇所のバス・連結ローリー転回部(1,500m間隔)、48箇所の停車帯(500m間隔)。
○センターエリア・ランブルストリップ。
○トンネル内路測通信。
○トンネル内携帯電話使用可能。
○トンネル内外での通行車両モニター・計測システム
○トンネル常時モニター
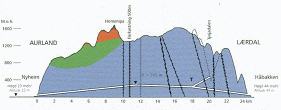
図3.地質図
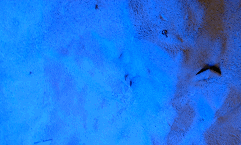
図4.ロックボルト工
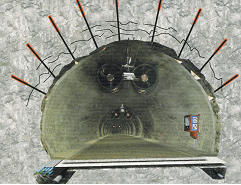
図5. トンネル断面図
〒060-0051 札幌市中央区南3条東1丁目4番地
Phone: (011) 213-0671
Fax: (011) 233-0090